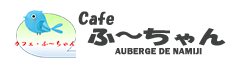BLOG
![]()
2017-07-17 22:18
私が子供の頃、佐田岬半島、ことに私の村周辺は段々畑で、平地がなく、農作のメインは、はだか麦と芋でした。地形的に、米作りが難しかったのです。
収入源としてのはだか麦と芋の出荷に追われる傍ら、農家の女たちは、家庭の食のための、みそやひがし芋、かんころとよばれた乾燥芋をつくっていました。
かつては、どの家でもその家の一年分の味噌作りをしていたものですが、今日では、その手間や、道具、場所の問題もあり、さらに気軽にスーパーで手に入るため、殆ど見られなくなりました。
子供の頃から、手作りの味噌を食べてきて、その味を忘れられず、できるかぎり引き継いでいきたいと願う、4名の主婦の味噌作りが、ここ数年、緒方家で梅雨のこの時期におこなわれています。麦味噌はこの地方の伝統で、少し甘めであることが特徴です。味噌作りの取材をさせて頂きましたのでレポートします。
味噌作り材料:
丸麦(はだか麦)
米(もち米)
米麹
大豆
塩
味噌作り初日
丸麦と米を洗ってザルにとり布を敷いた蒸し器に入れ、蒸し上げる。緒方家では昔ながらのかまどと羽釜を使っている。
羽釜から湯気が出てから約10~15分。蒸しあがった丸麦と米をむしろにとり、まぜながら冷ます。
少し冷ましてから、種麹を振り混ぜる。
むしろあるいは箱に移し、紙、むしろをかぶせ、さらに布団をかけて寝かせる。高温、湿度の高い部屋が良い。











左前から:よねちゃん、ふみちゃん、後ろ左からよしえさん、きょうこさん(味噌作りの先生役)素敵な仲間です。
味噌作り2日目
約24時間寝かせた後発酵した ’豆板’ (発酵して表面に白い花が咲いた状態)を混ぜ合わせる。 ’一度起こす’ と言うそうです。潰さず、混ぜるだけ。
室温37℃~38℃、豆板の温度、40℃~42℃位
一度起こして混ぜると温度が下がり、熟して柔らかくなり早く食べれるとのこと。
熟すことを’つわらす’と表現していました。
もう一度寝かせる。


味噌作り3日目(最終日)
一晩水につけておいた大豆を炊いて、柔らかくなったら、ミンチ器にかける。
再度発酵した豆板を器に移し、ミンチにした大豆を混ぜ合わせ、よく練り込む。(潰していく)
味噌の状態になったら、空気を抜きながら丸めて保存桶にいれ、腐りどめ、変色止めのために、上から塩をふりかける。
2~3週間位寝かせて出来上がり。





この味噌を使った代表的な郷土料理に、’さつま汁’があります。
あじやべらの魚を焼いて、身をほぐし、すり鉢で味噌、ピーナッツをあわせて擦り込み、水または、魚の残った骨やあらで取っただし汁をくわえて、麦をまぜたご飯にかけて、薬味として、ネギやごまをのせて食べます。






3日間の味噌作りを見学させて頂きながら、かつての村の人々が、畑仕事の合間や、雨の日に、家族ぐるみで、あるいはご近所が集まって、こうした作業を共同でしていた時代があったことを実感しました。緒方家のように、作業ができる広い庭があり、納屋や、家の中の片隅を作業場にして、朝夕発酵の香りとともに生活をしていた時代。防腐剤も、化学調味料も入らない、健全な食と、祖母や母の手のぬくもりが感じられる食。当たり前の時代だったのでしょう。
私は今回、味噌作りがこんに大変な労働であることを体験させて頂きました。今日、手軽に手に入る食材、自由な時間、便利な機器、私達の生活は、子供の頃よりずっと豊かに、贅沢になりました。しかし、豊かさの質はどうだろうか?そして、私達が本当に豊かさを感じているだろうか。手作りの味噌の味はもちろん、今回は人生の’味’をたっぷり感じさせて頂きました。
味噌作りは,各家庭に寄って、作る時期、作り方が多少異なるそうです。
収入源としてのはだか麦と芋の出荷に追われる傍ら、農家の女たちは、家庭の食のための、みそやひがし芋、かんころとよばれた乾燥芋をつくっていました。
かつては、どの家でもその家の一年分の味噌作りをしていたものですが、今日では、その手間や、道具、場所の問題もあり、さらに気軽にスーパーで手に入るため、殆ど見られなくなりました。
子供の頃から、手作りの味噌を食べてきて、その味を忘れられず、できるかぎり引き継いでいきたいと願う、4名の主婦の味噌作りが、ここ数年、緒方家で梅雨のこの時期におこなわれています。麦味噌はこの地方の伝統で、少し甘めであることが特徴です。味噌作りの取材をさせて頂きましたのでレポートします。
味噌作り材料:
丸麦(はだか麦)
米(もち米)
米麹
大豆
塩
味噌作り初日
丸麦と米を洗ってザルにとり布を敷いた蒸し器に入れ、蒸し上げる。緒方家では昔ながらのかまどと羽釜を使っている。
羽釜から湯気が出てから約10~15分。蒸しあがった丸麦と米をむしろにとり、まぜながら冷ます。
少し冷ましてから、種麹を振り混ぜる。
むしろあるいは箱に移し、紙、むしろをかぶせ、さらに布団をかけて寝かせる。高温、湿度の高い部屋が良い。











左前から:よねちゃん、ふみちゃん、後ろ左からよしえさん、きょうこさん(味噌作りの先生役)素敵な仲間です。
味噌作り2日目
約24時間寝かせた後発酵した ’豆板’ (発酵して表面に白い花が咲いた状態)を混ぜ合わせる。 ’一度起こす’ と言うそうです。潰さず、混ぜるだけ。
室温37℃~38℃、豆板の温度、40℃~42℃位
一度起こして混ぜると温度が下がり、熟して柔らかくなり早く食べれるとのこと。
熟すことを’つわらす’と表現していました。
もう一度寝かせる。


味噌作り3日目(最終日)
一晩水につけておいた大豆を炊いて、柔らかくなったら、ミンチ器にかける。
再度発酵した豆板を器に移し、ミンチにした大豆を混ぜ合わせ、よく練り込む。(潰していく)
味噌の状態になったら、空気を抜きながら丸めて保存桶にいれ、腐りどめ、変色止めのために、上から塩をふりかける。
2~3週間位寝かせて出来上がり。





この味噌を使った代表的な郷土料理に、’さつま汁’があります。
あじやべらの魚を焼いて、身をほぐし、すり鉢で味噌、ピーナッツをあわせて擦り込み、水または、魚の残った骨やあらで取っただし汁をくわえて、麦をまぜたご飯にかけて、薬味として、ネギやごまをのせて食べます。






3日間の味噌作りを見学させて頂きながら、かつての村の人々が、畑仕事の合間や、雨の日に、家族ぐるみで、あるいはご近所が集まって、こうした作業を共同でしていた時代があったことを実感しました。緒方家のように、作業ができる広い庭があり、納屋や、家の中の片隅を作業場にして、朝夕発酵の香りとともに生活をしていた時代。防腐剤も、化学調味料も入らない、健全な食と、祖母や母の手のぬくもりが感じられる食。当たり前の時代だったのでしょう。
私は今回、味噌作りがこんに大変な労働であることを体験させて頂きました。今日、手軽に手に入る食材、自由な時間、便利な機器、私達の生活は、子供の頃よりずっと豊かに、贅沢になりました。しかし、豊かさの質はどうだろうか?そして、私達が本当に豊かさを感じているだろうか。手作りの味噌の味はもちろん、今回は人生の’味’をたっぷり感じさせて頂きました。
味噌作りは,各家庭に寄って、作る時期、作り方が多少異なるそうです。
![]()
2017-06-25 08:59
ターシャ・テューダーはアメリカの絵本作家。同時にスローライフの元祖と言われ、ナチュラルライフを送るターシャの生き方はガーデナーの憧れであり、世界の人々に知られています。ターシャ・テューダーの世界を彷彿させる自然の庭が、佐田岬半島のほぼ真ん中,高茂に開放されていて、ターシャの生き方に共感するターシャフアン、ガーデナー、そして、自然を草花を愛し、あるいは自然の中にただ身をおいてくつろぎたい人々を惹き付けています。。高茂は芸能人、はるな愛の両親が、開発団の一員として住んでいたことで、近年地元TVでも紹介された地域。大手企業、ダイワハウスグループが全国14箇所に展開するスローライフをスローガンとしたリゾートのひとつで、日本各地からこの地に惹かれた人々が、定住あるいは別荘として、趣向を凝らした家を建てています。
。ここに17年前に神戸から一組のご夫婦が移住してきました。大利ご夫妻です。およそ1000坪の広大な敷地に理想とする家を建て、荒れ地にちかい敷地内の木を切り、草を刈り、少しづつ、現在の自然の庭を作り上げてきました。お二人はターシャ・テューダー同様、自然の営み、自然の力を理解し、その中での暮らしを楽しんでいらっしゃるようです。
様々な人生を生きてる多くの人々が、しばしでも憩いとなることを願い、ここを訪れる人々を心より歓迎して下さっています。さらに、大利夫人の植物の知識は、単なる博識ではなく、地元の呼び名や、それにまつわる話、移住してから歩き回った佐田岬半島の山々や村など話題は多岐に渡り、庭をご案内頂きながら、飽きることなく楽しめます。
自然故に、四季折々、雨の日、晴れの日、朝、夕方と表情を変える庭。ヤマガラや目白、カワラヒワなど、佐田岬の自然を凝縮したような鳥たちの訪れもここならでは。海のイメージの強い佐田岬半島のもう一つの魅力が凝縮されています。
庭はいつでも自由に散策できるよう開放して下さっています。お天気のいい一日、お茶を持ち、あるいはお弁当を持ち、あるいは本を抱えて、東屋で爽やかな風と鳥の声、折々の花や木々を楽しみながら、スローな一日を過ごしてはいかがでしょうか?
まず、ターシャ・テューダーのパネルが出迎え、大利家の自然の庭へアプローチ












。ここに17年前に神戸から一組のご夫婦が移住してきました。大利ご夫妻です。およそ1000坪の広大な敷地に理想とする家を建て、荒れ地にちかい敷地内の木を切り、草を刈り、少しづつ、現在の自然の庭を作り上げてきました。お二人はターシャ・テューダー同様、自然の営み、自然の力を理解し、その中での暮らしを楽しんでいらっしゃるようです。
様々な人生を生きてる多くの人々が、しばしでも憩いとなることを願い、ここを訪れる人々を心より歓迎して下さっています。さらに、大利夫人の植物の知識は、単なる博識ではなく、地元の呼び名や、それにまつわる話、移住してから歩き回った佐田岬半島の山々や村など話題は多岐に渡り、庭をご案内頂きながら、飽きることなく楽しめます。
自然故に、四季折々、雨の日、晴れの日、朝、夕方と表情を変える庭。ヤマガラや目白、カワラヒワなど、佐田岬の自然を凝縮したような鳥たちの訪れもここならでは。海のイメージの強い佐田岬半島のもう一つの魅力が凝縮されています。
庭はいつでも自由に散策できるよう開放して下さっています。お天気のいい一日、お茶を持ち、あるいはお弁当を持ち、あるいは本を抱えて、東屋で爽やかな風と鳥の声、折々の花や木々を楽しみながら、スローな一日を過ごしてはいかがでしょうか?
まず、ターシャ・テューダーのパネルが出迎え、大利家の自然の庭へアプローチ












![]()
2017-06-03 17:06
ゴールデンウィ-クのよく晴れた一日、佐田岬灯台へいった。2017年4月1日、佐田岬灯台は点灯100周年を迎えた。
記念事業の一環として、佐田岬灯台のお化粧直し、そして、灯台の下にある小さな島、御籠島を陸続きで行けるようにし、モニュメントを建てた。それを起爆剤として、町は佐田岬、伊方町のプロモーションに邁進している。
佐田岬灯台と対岸の佐賀関、関崎灯台までの距離はわずか13km。20世紀初頭の外国船の来航や日本の海運業が盛んになったことで灯台の必要性が高まり、まずは佐賀関の関崎灯台が1901年に建てられ、そして、1918年に佐田岬灯台が点灯した。佐田岬半島と佐賀関の間の豊予海峡は「速水の瀬戸」と呼ばれ、潮流の速さと岩礁の多いことで航行の難所とされていた。(さだみさきフリークVol.2 町見郷土館発行資料より)灯台の明かりは、航行する船の船乗りにとって、まさに命の光となったことと想像できる。
佐田岬半島の長さは俗に13里と言われ、13里は、現在の測量単位で約52km。三崎港までは国道197号線の快適なドライブコースとなっているが、三崎港から灯台までの道はなかなかの難所。曲がりくねった道が約30分程続く。灯台の駐車場から、灯台まではさらに徒歩約20分の距離。ここがまたまた難所。下って、登って下って登る、ちょっと辛い道。しかし、辛さの中に楽しみもある。木陰の心地よい遊歩道、時折見える、瀬戸内海、太平洋の海、自然の植物など、ちょっとしたご褒美だ。
やがて灯台が見えてくる。灯台への階段を登る。あの、素晴らしいパノラマに出逢うための最後の試練だ。
灯台への遊歩道を歩く




これまでもその感動の為に、何度か足を運んだ。しかし、今回、さらなる感動に出会った。灯台の階段下を右手の道を下っていくと御籠島へと続く。養殖池をまわり、御籠島のスロープを登ると豊予海峡のパノラマが広がり、振り向けば佐田岬灯台が凛とした白亜の姿を現す。よく晴れた日で、豊予海峡の向こうに、九州の佐賀関や別府が見渡せた。点灯100年祭のイヴェントの一つとして’永遠の光’と名付けられたモニュメントが建っている。
しかし、ただ風光明媚を満喫するだけにはさせてくれなかった。御籠島には、第二次世界大戦の爪痕,洞窟式砲台跡があり、砲台のレプリカが置かれている。佐田岬半島の瀬戸内海側の対岸には、呉港があり、戦時中、佐田岬半島の村々の上空を戦闘機が飛んでいったと、父母から聞いたことがある。佐田岬半島の沿岸を中心に、大正末期から昭和初期にかけて,砲台や監視所が作られ、今日もその痕跡を見ることができる。
2016年、観光プロモーションの一環として、日本ロマンチスト協会&日本財団による、’恋する灯台’プロジェクトが開始、佐田岬灯台が日本の21に設定された一つに選ばれた。日本最西端の日本一長い半島の白亜の灯台がロマンに満ちているということだろう。今回は、怠けて行かなかったけれど、灯台の手前に椿山展望台があり、そこは恋人たちのデートコースとして、ハートのオブジェが設置されている。
佐田岬灯台は日本の灯台100選にも選ばれている。1998年(平成10年)11月1日、海上保安庁が、灯台記念日のイヴェントとして、一般から募集した灯台100選である。
佐田岬半島が風光明媚な国立公園であることを、意外と地元のは意識していないのではないだろうか。もっともっと、誇りに思い、もっともっと自慢して、我が村への、我が故郷への想いを高めて欲しい。(資料の一部は、町見郷土館発行のさだみさきフリークVol.2を参照にしています。)
御籠島へ










灯台展望台にて

記念事業の一環として、佐田岬灯台のお化粧直し、そして、灯台の下にある小さな島、御籠島を陸続きで行けるようにし、モニュメントを建てた。それを起爆剤として、町は佐田岬、伊方町のプロモーションに邁進している。
佐田岬灯台と対岸の佐賀関、関崎灯台までの距離はわずか13km。20世紀初頭の外国船の来航や日本の海運業が盛んになったことで灯台の必要性が高まり、まずは佐賀関の関崎灯台が1901年に建てられ、そして、1918年に佐田岬灯台が点灯した。佐田岬半島と佐賀関の間の豊予海峡は「速水の瀬戸」と呼ばれ、潮流の速さと岩礁の多いことで航行の難所とされていた。(さだみさきフリークVol.2 町見郷土館発行資料より)灯台の明かりは、航行する船の船乗りにとって、まさに命の光となったことと想像できる。
佐田岬半島の長さは俗に13里と言われ、13里は、現在の測量単位で約52km。三崎港までは国道197号線の快適なドライブコースとなっているが、三崎港から灯台までの道はなかなかの難所。曲がりくねった道が約30分程続く。灯台の駐車場から、灯台まではさらに徒歩約20分の距離。ここがまたまた難所。下って、登って下って登る、ちょっと辛い道。しかし、辛さの中に楽しみもある。木陰の心地よい遊歩道、時折見える、瀬戸内海、太平洋の海、自然の植物など、ちょっとしたご褒美だ。
やがて灯台が見えてくる。灯台への階段を登る。あの、素晴らしいパノラマに出逢うための最後の試練だ。
灯台への遊歩道を歩く




これまでもその感動の為に、何度か足を運んだ。しかし、今回、さらなる感動に出会った。灯台の階段下を右手の道を下っていくと御籠島へと続く。養殖池をまわり、御籠島のスロープを登ると豊予海峡のパノラマが広がり、振り向けば佐田岬灯台が凛とした白亜の姿を現す。よく晴れた日で、豊予海峡の向こうに、九州の佐賀関や別府が見渡せた。点灯100年祭のイヴェントの一つとして’永遠の光’と名付けられたモニュメントが建っている。
しかし、ただ風光明媚を満喫するだけにはさせてくれなかった。御籠島には、第二次世界大戦の爪痕,洞窟式砲台跡があり、砲台のレプリカが置かれている。佐田岬半島の瀬戸内海側の対岸には、呉港があり、戦時中、佐田岬半島の村々の上空を戦闘機が飛んでいったと、父母から聞いたことがある。佐田岬半島の沿岸を中心に、大正末期から昭和初期にかけて,砲台や監視所が作られ、今日もその痕跡を見ることができる。
2016年、観光プロモーションの一環として、日本ロマンチスト協会&日本財団による、’恋する灯台’プロジェクトが開始、佐田岬灯台が日本の21に設定された一つに選ばれた。日本最西端の日本一長い半島の白亜の灯台がロマンに満ちているということだろう。今回は、怠けて行かなかったけれど、灯台の手前に椿山展望台があり、そこは恋人たちのデートコースとして、ハートのオブジェが設置されている。
佐田岬灯台は日本の灯台100選にも選ばれている。1998年(平成10年)11月1日、海上保安庁が、灯台記念日のイヴェントとして、一般から募集した灯台100選である。
佐田岬半島が風光明媚な国立公園であることを、意外と地元のは意識していないのではないだろうか。もっともっと、誇りに思い、もっともっと自慢して、我が村への、我が故郷への想いを高めて欲しい。(資料の一部は、町見郷土館発行のさだみさきフリークVol.2を参照にしています。)
御籠島へ










灯台展望台にて

![]()
2017-05-26 19:41
五月晴の早朝、しらす漁体験をさせて頂いた。我が村塩成のシラス漁は木嶋水産と田中水産があり、隣村には朝日共販がある。我が家の窓から見える早朝の海は、3社のしらす船で賑わっている。木嶋水産と田中水産は家内工業規模の操業。朝日共販は地元では大企業と言え、日本全国を視野に操業している。
木嶋水産も田中水産も地元のおばちゃん、男たちが手作業で丁寧に,しらすにまじるイカや雑魚を取り除き、外の網で天日干しをし、注文に応じて、送ったり、搬入したり、お客の対応をしている。
今回は、木嶋水産のシラス漁船に乗せて頂いた。
シラス漁は3艘が1セットとなっているという。二艘が網を張り,一艘が、引き上げ運搬を担当する。
私達が乗せていただいたのは運搬の船。引き上げられたばかりのしらすは透き通っていて感動!何とも言えぬ食欲をそそる。私達が体験させて頂いた日は、ぶと(くらげ)がいっぱい網に入っていて、それを取り除くのに往生していた。
海の男達のファッションもなかなか素敵だ。つなぎはそれぞれ色を変えて、海の青と日焼けした肌によくあっている。無駄のない動き、当たり前かもしれないけれど、息の合った作業が印象的。
しらす船からの佐田岬半島の景色はまさに絶景!。海が太陽の光でキラキラと輝き眩しい。白波が美しい弧を描く。かもめがスターのようにその光景に溶け込んでくる。佐田岬半島の流れるような5月の緑。点在する小さな村。私達の暮らしがここにある。
つい最近まで、しらすが全然獲れなくて、工場の人達は手もちぶたさだった。ここにきて、どんどん獲れて、今度は忙しすぎて皆疲れが顔にでてきているという。シラス漁は4月から11月頃が最盛期だという。塩成のシラス漁は2月は休漁期間としているそうだ。
自然の営みの中で生業することの難しさ。けれど、自然の恵を身体全体で感じ、感謝していることだろう。
私達も同様、彼らの仕事があって、自然の恵を頂けることに、心から感謝したい。












木嶋水産も田中水産も地元のおばちゃん、男たちが手作業で丁寧に,しらすにまじるイカや雑魚を取り除き、外の網で天日干しをし、注文に応じて、送ったり、搬入したり、お客の対応をしている。
今回は、木嶋水産のシラス漁船に乗せて頂いた。
シラス漁は3艘が1セットとなっているという。二艘が網を張り,一艘が、引き上げ運搬を担当する。
私達が乗せていただいたのは運搬の船。引き上げられたばかりのしらすは透き通っていて感動!何とも言えぬ食欲をそそる。私達が体験させて頂いた日は、ぶと(くらげ)がいっぱい網に入っていて、それを取り除くのに往生していた。
海の男達のファッションもなかなか素敵だ。つなぎはそれぞれ色を変えて、海の青と日焼けした肌によくあっている。無駄のない動き、当たり前かもしれないけれど、息の合った作業が印象的。
しらす船からの佐田岬半島の景色はまさに絶景!。海が太陽の光でキラキラと輝き眩しい。白波が美しい弧を描く。かもめがスターのようにその光景に溶け込んでくる。佐田岬半島の流れるような5月の緑。点在する小さな村。私達の暮らしがここにある。
つい最近まで、しらすが全然獲れなくて、工場の人達は手もちぶたさだった。ここにきて、どんどん獲れて、今度は忙しすぎて皆疲れが顔にでてきているという。シラス漁は4月から11月頃が最盛期だという。塩成のシラス漁は2月は休漁期間としているそうだ。
自然の営みの中で生業することの難しさ。けれど、自然の恵を身体全体で感じ、感謝していることだろう。
私達も同様、彼らの仕事があって、自然の恵を頂けることに、心から感謝したい。












![]()
2017-04-28 22:34
佐田岬半島のほぼ真ん中辺り、瀬戸内海を望む小さな村’大江’があります。佐田岬半島の瀬戸内海側は、リアス式海岸になっていて、深い入江が多く、大江も美しい深い入江の中に斜面に沿って家々が連なっています。
佐田岬半島の太平洋側の海は明るい空色をしていて穏やかなときが多いのにくらべ、瀬戸内海側、大江の入江は、深い緑色をたたえ、ざわざわと波立っていることも多いようですが、なんとも言えぬ美しさです。
海辺の側にN氏ご夫妻の日本家屋の良さをたっぷり味わえる住まいがあります。大江に生まれ育ったN氏の、故郷への想いは彼の生き様そのものです。地域の良さをアピールするために結成された佐田岬見つけ隊、国際交流活動等のほか、退職後は自宅の周りの荒れ地を整備、美化に努め、先代から受け継いだ柑橘畑を手入れして、誰もが気楽に自然を楽しめる場にしたいと、草刈りから山小屋の補修作業、道づくりと何でもこなしていきます。
一方、N氏の妻は、自然の庭作りに余念がない。N氏が海から流木を拾って垣根やオブジェを作り、妻は、草引きに明け暮れる日々。美しい花壇を作るのではなく、できるだけ自然に自生している草花の中を散策できるよう工夫をしている。’江里花だん’と名付けられた庭は、大江の里の意。彼らのこだわりがある。
そして、二人の夢は、ここに誰もが、お弁当を持って、あるいは、自由にお茶を楽しんで、くつろぎのひと時を過ごして頂き、大江の村を知っていただくこと。大江の村の自然の美しさ、豊かさを体感して頂くこと。大江LOVERのご夫婦です。






佐田岬半島の太平洋側の海は明るい空色をしていて穏やかなときが多いのにくらべ、瀬戸内海側、大江の入江は、深い緑色をたたえ、ざわざわと波立っていることも多いようですが、なんとも言えぬ美しさです。
海辺の側にN氏ご夫妻の日本家屋の良さをたっぷり味わえる住まいがあります。大江に生まれ育ったN氏の、故郷への想いは彼の生き様そのものです。地域の良さをアピールするために結成された佐田岬見つけ隊、国際交流活動等のほか、退職後は自宅の周りの荒れ地を整備、美化に努め、先代から受け継いだ柑橘畑を手入れして、誰もが気楽に自然を楽しめる場にしたいと、草刈りから山小屋の補修作業、道づくりと何でもこなしていきます。
一方、N氏の妻は、自然の庭作りに余念がない。N氏が海から流木を拾って垣根やオブジェを作り、妻は、草引きに明け暮れる日々。美しい花壇を作るのではなく、できるだけ自然に自生している草花の中を散策できるよう工夫をしている。’江里花だん’と名付けられた庭は、大江の里の意。彼らのこだわりがある。
そして、二人の夢は、ここに誰もが、お弁当を持って、あるいは、自由にお茶を楽しんで、くつろぎのひと時を過ごして頂き、大江の村を知っていただくこと。大江の村の自然の美しさ、豊かさを体感して頂くこと。大江LOVERのご夫婦です。

誰もが自由にここに来てお茶をして欲しい。

手作りの橋。小川が流れる

深い緑色をたたえた瀬戸内海

海からの流木でオブジェを!

木のイスのぬくもりの中でお茶しませんか?

近い将来、ミカン畑の中でカフェOPENを夢見て!