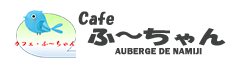BLOG
![]()
2018-02-20 20:40
村の、村たらしめるもののひとつ(私の勝手な理論ですが)が昔から受け継がれてきた宗教的なイヴェント。神道のイヴェントの代表は、収穫を祝う秋祭りや無病息災を願う儀式、そして6世紀に日本に伝えられた仏教が時代を経、地方の気候風土によって、各地の村に根付いた仏教イヴェント。子供の頃から意味もわからず、大人にまじって儀式に参加していた我が村のその一つのイヴェントが念仏はじめ。我が村では毎年1月16日に庵寺でおこなわれる。庵寺は寺の末庵でほとんどの村に存在し、この地方では、多分お庵がなまったものだろう、’おわん’と呼ばれて、村人に最も密着した存在だ。
わが村塩成の庵寺は、三机にある臨済宗妙心寺派長養寺の末庵で、臨海山宝手庵と号される。本尊は千手観音菩薩で、1717年創建と記録。が、私はお庵の中に面白い札を発見した。お札によれば’臨海山宝手庵紀元2616年再建’とある。現在が2018年ということは、単なる間違いで書かれたのか、もしくはお釈迦様誕生から2616年という意味なのか、ちょっと歴史のロマンを感じる。




信仰深い村人、お地蔵様に前掛けをかけて。 千手観音様の隣には弘法大師様が。
わが村のお庵は江戸時代の藩政において、寺子屋として藩政教育の場であり、明治15年には三机第一分校となり、明治25年(1892年)、塩成小学校開校まで教育の場として重要な役割を果たしてきたとある。こんな小さな、今日では忘れられているかと思うような庵寺にこんな歴史があることに感動している。
私が子供の頃、庵主様がいて近所のご老人たちが、縁側でおしゃべりをしていた記憶がわずかに残っている。お庵は村人の社交の場でもあった。わが村のように、かつては庵主様がいたようだが、今日では殆どが不在で、村人たちが管理している。


草履を編む


この村にはこんな大きな草履を履く巨人がいるぞ! リーダーが鐘をたたいて念仏を先導


数珠を回しながら、般若心経を。 念仏を唱える
我が村の念仏初めは、念仏の前に、大きな藁草履を編んで、村の入口に立てかける。いつ頃始めたものかわからないが、この草履の意は、よそ者に、’この村にはこんな大きな草履を履く巨人がいるんだぞ! 悪さはできないぞ! ’という脅しだそうだ。我が村だけでなく、佐田岬半島の殆どの村々の入り口にみかけられる。今の我々は笑ってしまうかわいい防犯だが、当時は大真面目だったのだろう。
そのあとで、’村の念仏’を唱え、さらに、般若心経を唱えながら数珠の輪をまわす。数珠の輪は各村によって若干異なっているようだが、基本的に108の数珠がつながれているそうだ。
私が村の村たらしめるという根拠は、私が子供の頃まで、殆どの村人が庵寺に集まり、皆で粛々とこのイヴェントをしており、村人たちの絆となっていたと思うから。今日では、様々な理由があることだろうが、イヴェントの役回りの人以外、村人は6~7人ほどもいるかいないか。こんな小さな村にいて、近所の人の安否さえも、入院をするとか、救急車が来るとかして、噂にならなければ知らないということも多い。大きな草鞋を編める人も、念仏や般若心経をそらで唱えられる人も殆ど居なくなり、数年後には誰もいなくなり、イヴェントの形は変わらざるをえないかもしれない。村そのものの存続の危機に直面する日も遠くない今日、せめて今はかつての村の人々の想いを受け継いで欲しい。
わが村塩成の庵寺は、三机にある臨済宗妙心寺派長養寺の末庵で、臨海山宝手庵と号される。本尊は千手観音菩薩で、1717年創建と記録。が、私はお庵の中に面白い札を発見した。お札によれば’臨海山宝手庵紀元2616年再建’とある。現在が2018年ということは、単なる間違いで書かれたのか、もしくはお釈迦様誕生から2616年という意味なのか、ちょっと歴史のロマンを感じる。




信仰深い村人、お地蔵様に前掛けをかけて。 千手観音様の隣には弘法大師様が。
わが村のお庵は江戸時代の藩政において、寺子屋として藩政教育の場であり、明治15年には三机第一分校となり、明治25年(1892年)、塩成小学校開校まで教育の場として重要な役割を果たしてきたとある。こんな小さな、今日では忘れられているかと思うような庵寺にこんな歴史があることに感動している。
私が子供の頃、庵主様がいて近所のご老人たちが、縁側でおしゃべりをしていた記憶がわずかに残っている。お庵は村人の社交の場でもあった。わが村のように、かつては庵主様がいたようだが、今日では殆どが不在で、村人たちが管理している。


草履を編む


この村にはこんな大きな草履を履く巨人がいるぞ! リーダーが鐘をたたいて念仏を先導


数珠を回しながら、般若心経を。 念仏を唱える
我が村の念仏初めは、念仏の前に、大きな藁草履を編んで、村の入口に立てかける。いつ頃始めたものかわからないが、この草履の意は、よそ者に、’この村にはこんな大きな草履を履く巨人がいるんだぞ! 悪さはできないぞ! ’という脅しだそうだ。我が村だけでなく、佐田岬半島の殆どの村々の入り口にみかけられる。今の我々は笑ってしまうかわいい防犯だが、当時は大真面目だったのだろう。
そのあとで、’村の念仏’を唱え、さらに、般若心経を唱えながら数珠の輪をまわす。数珠の輪は各村によって若干異なっているようだが、基本的に108の数珠がつながれているそうだ。
私が村の村たらしめるという根拠は、私が子供の頃まで、殆どの村人が庵寺に集まり、皆で粛々とこのイヴェントをしており、村人たちの絆となっていたと思うから。今日では、様々な理由があることだろうが、イヴェントの役回りの人以外、村人は6~7人ほどもいるかいないか。こんな小さな村にいて、近所の人の安否さえも、入院をするとか、救急車が来るとかして、噂にならなければ知らないということも多い。大きな草鞋を編める人も、念仏や般若心経をそらで唱えられる人も殆ど居なくなり、数年後には誰もいなくなり、イヴェントの形は変わらざるをえないかもしれない。村そのものの存続の危機に直面する日も遠くない今日、せめて今はかつての村の人々の想いを受け継いで欲しい。
![]()
2017-12-10 22:26
10月下旬から12月後半にかけて、温州みかんの収穫期。みかん農家の皆様の一年でもっともハードな季節です。日本のみかんの生産地は、日本のみかん発祥の地和歌山を始め、愛媛、静岡、熊本、そして長崎などとなっていますが、愛媛みかんの定評はもちろん、その中でも我が西宇和郡のみかんは最高品質であると自負しています。太陽と潮風、段々畑の石垣の照り返しがこの地方の美味しいみかんを育てると言われています。温暖な気候に、潮風、南に面した段々畑の日照時間と日照量が、糖度と酸味のバランスのよい美味しいみかんを作るのだそうです。
’暖かいこたつにみかん’はなんとなくほのぼのとした日本の冬の風物詩。私は3年前からみかん採りの手伝いをして、そんな風物詩を作り出しているみかん農家のご苦労と手間暇を知ることができました。みかん農家に限らず、りんごの農家も、柿の農家も、冬の鍋に欠かせない白菜やネギ、きのこの農家も大変なご苦労をしていることが偲ばれます。
ここでは私が体験したみかん農家の暮らしを是非皆様に知って頂きたいと思います。




一度ハサミを入れてきったみかんを他のみかんを傷つけないように2度切りする。


採れたみかんの運搬は何よりの重労働! 山でのランチ、美しい風景とおいしい空気が何より!




みかん畑から宇和海を望む。絶景! イノシシの被害、台風被害、そして空からは鳥の被害!
’暖かいこたつにみかん’はなんとなくほのぼのとした日本の冬の風物詩。私は3年前からみかん採りの手伝いをして、そんな風物詩を作り出しているみかん農家のご苦労と手間暇を知ることができました。みかん農家に限らず、りんごの農家も、柿の農家も、冬の鍋に欠かせない白菜やネギ、きのこの農家も大変なご苦労をしていることが偲ばれます。
ここでは私が体験したみかん農家の暮らしを是非皆様に知って頂きたいと思います。




一度ハサミを入れてきったみかんを他のみかんを傷つけないように2度切りする。


採れたみかんの運搬は何よりの重労働! 山でのランチ、美しい風景とおいしい空気が何より!




みかん畑から宇和海を望む。絶景! イノシシの被害、台風被害、そして空からは鳥の被害!
みかん農家の一年:
11月から温州みかんの最盛期、1月から5月頃までポンカンやデコポン、清美など晩柑と呼ばれる柑橘類の収穫。1月消毒、同時にみかんの木の伐採作業を随時、6月摘果、木の枝の剪定、草刈りは年に数回、6月から9月まで1ヶ月に1回の割合で消毒、害虫がでれば更に消毒回数が増える。一年中仕事が絶えることはありません。
収穫期の、あるみかん農家の主婦の一日を伺いました。
起床5:00,弁当作りと義父の朝食、昼食準備。6:30みかん山へ。みかん採り開始7:00~7:30。10:00 みかん採りのアルバイターへのお茶準備、午後4:00、みかん採り終了、義父の夕食準備をしてすぐに倉庫へ。みかんの選別、箱詰め。午後9:00、夕食準備、食事、風呂、洗濯。午前1:00~2:00、入出金管理、同封の請求書作成、翌日の段取り。2:00就寝。収穫期の2ヶ月余り、平均睡眠時間は約3時間から4時間とのこと。


山での仕事を終えてから倉庫へ。みかんの選別。この作業は長年の経験で培った目が必要。誰でもできる作業ではない
長年身をもってみかん農家の経営にたずさわってきたここのご主人は、息子を後継者にしたくないといい、そして、次に生まれたときは農家にはならないという。みかん農家というハードな仕事は自分の代だけでいいと。みかん農家の高齢化、後継者不足によって年々みかん農家は減少し、みかんの畑地も荒れてきています。そして、イノシシやハクビシンの被害が、ますす増え、さらには台風による被害も大きかったといいます。
それでも畑に生きる人々は、体は酷使しながらも、太陽の下で働き、甘いみかんのできた喜び、子供や孫との時間を楽しみ、仕事の後の家での寛ぎに満たされているのでしょう、彼らの顔はとても明るくいいシワを刻んでいるように見えます。子どもたちは、そんな父母の背中を見て育ち、そして、誇りに思うことでしょう。
私は、こうした地方にあって、農家が農業で生計を立てられない、あるいは、農業を続けられない国は、決して豊かな国ではなく、国策で農業を守れない国に将来性はないと思います。なぜなら、農業は人間の命の根源であるから。